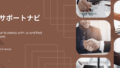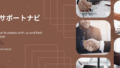日本の製造業を支える「地場産業」は、伝統技術と地域経済の基盤として、長きにわたり重要な役割を果たしてきました。しかし、人口減少、担い手不足、事業承継問題など、様々な課題が重くのしかかり、持続可能性が強く問われる時代となっています。
このような中で、地域の中小企業が連携し、工場や製造現場を一般に公開する取り組み――「地域一体型オープンファクトリー(以下、OF)」が、全国各地で注目を集めています。
本記事では、2025年3月に日本政策投資銀行関西支店が発行したレポート『地域一体型オープンファクトリーの可能性』から、OFの意義、活用方法、そして中小企業支援の視点からの活用可能性について詳しく解説していきます。
日本政策投資銀行関西支店 地域一体型オープンファクトリーの可能性https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/781dbbfc2b91ebc1b967cb450c9c532d.pdf
地場産業が今、直面している現実
まず私たちが理解すべきは、日本の地域に根ざした地場産業がどれだけ重要な存在であるかということです。日本の地場産業は、今治タオル、鯖江の眼鏡、燕三条の金属製品、西陣織など、国内外で高い評価を得る製品を生み出してきました。
しかし近年、このような産業を支える中小企業の数や出荷額は急速に減少しています。
- 製造業の事業所数は2002年比で大幅減少
- 従業員数は減少傾向、65歳以上の経営者比率は54.5%(2023年時点)
- 後継者未定率も37.9%に達するなど、事業承継問題が顕在化
多くの企業がOEMや下請けに依存した孤立型ビジネスモデルであることも課題です。こうした状況では最終顧客や異業種との接点が少なく、ニーズの変化や技術革新に柔軟に対応することが困難となります。
地域一体型オープンファクトリーとは何か?
地域一体型オープンファクトリーとは、地域内の複数企業が連携して製造現場を公開し、一般市民や観光客、ビジネスパーソンに「ものづくりの現場」を体験してもらうイベントです。
一社単独では難しい企画や運営も、地域ぐるみで取り組むことで実現可能になります。
- 地域住民との接点を生む
- 自社ブランドや地域ブランドの向上
- 社員のモチベーションアップ、インナーブランディング
- 異業種連携や新規事業創出のきっかけに
これらは単なるイベントに留まらず、地場産業の持続的発展を後押しする戦略的ツールとなるのです。
成功事例から学ぶ、地域一体型オープンファクトリーの真価

日本全国で実施されている成功事例の中から、特に注目すべき6つの取り組みをご紹介します。それぞれに独自の工夫と強みがあり、地場産業振興のリアルなヒントにあふれています。
福井県「RENEW」|地域産業×デザイン×観光の融合モデル
開催地:鯖江市、越前市、越前町
開始年:2015年
主な産業:眼鏡・漆器・和紙
参加企業数:118社(2024年)
来場者数:約48,000人
RENEWは、国内最大級のOFイベントとして知られています。特徴的なのは、イベントの主催が法人化された実行委員会(SOE)であること。また、地域外から学生やクリエイターを受け入れる「インターン制度」があり、若者が運営に深く関与している点も注目されます。
地場企業では、イベントを契機に自社ブランドの立ち上げやファクトリーショップの開設が相次ぎ、地元に新たな雇用も生まれました。
大阪府「FactorISM」|産官学金による広域連携型モデル
開催地:大阪府八尾市、東大阪市ほか
開始年:2020年
主な産業:歯ブラシ・金属加工・電子機器など
参加企業数:91社(2024年)
来場者数:17,600人
「みせるばやお」という会員制拠点を核とし、教育機関や地場大手企業と連携したプラットフォーム運営が大きな特徴です。
鉄道会社・小売・メディアなど異業種とのコラボが活発で、製造業の枠を超えた連携が生まれています。これにより、新卒採用が活性化し、大学との共同研究も増加しています。
山梨県富士吉田市|まちづくりとアートの融合による地域活性
開催地:富士吉田市
開始年:2016年(工場公開)/2021年(芸術祭)
主な産業:織物(富士山麓繊維産業)
来場者数:延べ26,000人(2024年)
地域おこし協力隊の移住者や学生、アーティストが中心となり、複層的な取り組みが行われています。
特に注目すべきは、産業をアートと融合させた「FUJI TEXTILE WEEK」。アーティストやバイヤーを招いた展示・体験を通じて、地域の織物産業が国内外に発信されています。
また、若者のUターンやIターン、移住者による起業など、ライフスタイルとしての地域参加が加速しています。
五泉ニットフェス(新潟県)|産地外人材の参画による柔軟な運営
ニット製造業が集積する五泉市では、地元だけでなく産地外からの参画者が企画・運営に関わることで、より柔軟で発展的なOFの形を実現しています。
「ウールラボ」や「産地遠征プログラム」など、教育とBtoB事業の両面を融合した取り組みが特徴的です。コロナ禍には、**リモート運営ボランティア「アンバサダー制度」**も立ち上がり、多様な関わり方が可能になりました。
スミファ(東京都墨田区)|地域金融機関の運営参画
墨田区の伝統的なものづくり企業が参加するOFイベント「スミファ」では、地域金融機関である東京東信用金庫が実行委員として参画しています。
金融支援だけでなく、デジタルスタンプラリーの企画や、広報活動への貢献など多様な支援がなされ、資金・人材の両面での課題を乗り越えています。
ひつじサミット尾州(愛知・岐阜)|ファンを「支援者」に変えるクラウドファンディング戦略
ウール繊維産地として知られる尾州エリアでは、クラウドファンディングによる資金調達とファン育成を両立させた「ひつじ団」を展開。
特別ツアーやSNS招待などを通じて、単なる支援者から**“地域を語れるサポーター”へとファン層を育成しています。さらに、鉄道会社と連携したトークイベント、産地間交流など他地域との連携による波及効果**も大きな成果となっています。
地域一体型オープンファクトリーが生む4つの効果
- ブランディング効果(短期)
→ 社員教育、社内モチベーション向上、広告コストの削減 - 社会的効果(中期)
→ 地域住民との連携、関係人口の創出、雇用の安定化 - 経済的効果(長期)
→ 自社ブランド創出、新規販路拡大、異業種連携による新規事業 - 文化的効果(継続)
→ 技術伝承、地域文化の発信、教育資源としての活用
万博を契機に、OFは次のステージへ
2025年の大阪・関西万博は、OFが国際的に注目されるまたとない機会です。すでに「Tech Tours Kansai」といった仕組みを通じて、海外企業との視察マッチングが動き出しています。
この機会に、OFを営業ツールやインバウンド施策として活用する視点が必要です。営業フェーズごとのターゲティングや、ビジネスマッチング機能を持たせることで、地域内中小企業のBtoB事業が加速します。
まとめ:見せる工場から、地域産業の未来を創る場へ
地域一体型オープンファクトリーは、単なる「製造現場の公開イベント」ではありません。
それは、地域の未来に向けた共創のプラットフォームであり、中小企業の成長戦略の核となる取り組みです。
今こそ、中小企業経営者と支援者が手を取り合い、「見せる」から「つながる」へ、そして「育てる地域産業」への一歩を踏み出す時です。