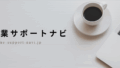近年、「リスキリング」や「学び直し」という言葉が経営の世界でも頻繁に取り上げられるようになりました。特に中小企業経営者にとって、社会や産業構造の急激な変化に対応するための学び直しは、もはや避けられない経営課題と言えます。
東京商工会議所が2025年5月~6月に実施した「経営者の学び直しに関するアンケート調査」では、中小企業経営者の取り組み状況や課題、さらにはヒアリングによる具体的な事例が明らかになりました。本記事では、その調査結果をもとに、学び直しの現状と課題、そして経営に与える効果を分かりやすく整理してご紹介します。
7割の経営者が「学び直し」に前向き
調査結果によると、経営者のうち50%が「すでに学び直しに取り組んでいる」と回答し、さらに20%が「今後2~3年以内に取り組みたい」と答えています。つまり、現在あるいは将来にわたり学び直しに積極的な経営者は全体の7割に達しており、学習意欲の高さがうかがえます。
ただし、この結果には注意も必要です。回答率が1.8%と低水準であることから、すでに学び直しに取り組んでいる、または関心のある層が積極的に回答した可能性が高く、実際の母集団全体ではもう少し低い水準であることが推測されます。
とはいえ、少なくとも経営者層の中で「学び直し」が重要視されつつあることは確かであり、企業経営における学びの在り方が変化していることを示しています。
学び直しのきっかけと内容
経営者が学び直しを始めた理由として最も多かったのは「事業を進める上で不足している知識やスキルを習得したかったから」(80%)。次いで「新しい分野への興味」(56%)が挙げられました。つまり、多くの経営者は外部からの圧力や推奨ではなく、自らの課題認識を原動力として学び直しに取り組んでいるのです。
具体的な学習内容としては、
- 「既存事業に必要な知識・スキル」(76%)
- 「新規事業に必要な知識・スキル」(55%)
- 「デジタル・ITに関する知識や資格」(55%)
が上位を占めており、経営の実務や事業成長に直結するテーマが中心です。一方で、語学や一般教養など、直接経営に関わらない分野は少数派にとどまっています。
これは裏を返せば、経営者が学び直しを「趣味」ではなく「経営戦略の一環」として捉えていることを意味します。
学び直しの効果と企業への影響
実際に学び直しを行った経営者からは、多面的な効果が報告されています。
最も多かったのは「自社の経営を俯瞰して見直し、将来像を考えられるようになった」(60%)。次いで「既存事業の生産性向上につながった」(46%)、「経営へのモチベーション向上」(45%)、「従業員の人材育成制度の改善」(44%)と続きました。
つまり、学び直しは経営者個人の知識獲得にとどまらず、組織全体の方向性や人材育成にまで影響を及ぼしています。また、学び直しをしている企業は新規事業に積極的であり、利益も上昇または維持傾向にあるという結果が示されており、学び直しが企業成長のドライバーとなっていることが確認されました。
学び直しの最大の課題 ― 「時間」と「費用」
しかし、課題も少なくありません。
学び直しに取り組む経営者の最大の悩みは「時間の確保」。経営者は日常的に多忙であり、学習時間を取ること自体が難しいという現実があります。また、すでに取り組んでいる経営者からは「費用負担が重い」(30%)という声もありました。
一方で、学び直しを行っていない経営者の理由としては「必要性を感じない」(35%)、「どの知識やスキルが必要か分からない」(32%)といった声が目立ちます。つまり、時間やコスト以前に「学ぶべき対象が曖昧」なことが、学び直しを始められない要因になっているケースもあるのです。
ヒアリング結果にみる具体的な実践事例

アンケートと並行して実施されたヒアリング調査では、学び直しに積極的に取り組んでいる経営者の生の声が紹介されています。
ファイン株式会社(製造業・22名)
経営戦略立案や財務知識の不足を痛感し、専門職大学院に通学。土日・夜間受講やオンライン併用で学びと業務を両立し、経営判断力を大きく向上させました。さらに、従業員に勉強会や人事評価制度を組み合わせる形で学習機会を提供し、社員の成長を後押ししています。
ひまわり福祉会(福祉・400名)
「私の知見以上に組織は大きくならない」という危機感を背景に、積極的に外部研修や経営者交流会へ参加。他法人の成功事例を研究し、自法人の経営改善に活用しました。さらに、従業員表彰制度を導入し、学び直しを組織文化として根付かせています。
鈴新株式会社(卸売業・18名)
49歳で急遽経営に参画し、MBAを取得。週末通学を通じて体系的な経営知識を習得しました。さらに従業員への英語研修を導入するなど、学び直しを自社全体の成長につなげています。
佐藤電研株式会社(製造業・6名)
東京都のDX講座を活用し、オンデマンド動画でスキマ時間に学習。システム導入や工程マニュアル化を進め、業務効率化と技術継承に成功しました。
これらの事例に共通しているのは、「経営者自身の危機感」と「学びの仕組み化」です。経営者が本気で学び直しに取り組むことで、組織全体の変革が実現しているのです。
今後の展望と支援の必要性
調査の自由意見では、「経営者への補助が少ない」「情報が分散しており探しにくい」「大学で学び直すための支援が欲しい」といった声が多く寄せられました。
実際、従業員向けのリスキリング支援は制度的に整いつつある一方で、経営者向けの支援は限定的です。しかし、企業の方向性を決定づけるのは経営者であり、経営者自身の学び直しが企業全体の競争力に直結することを考えれば、今後は政策的な支援強化が不可欠でしょう。
まとめ
今回の調査から見えてきたのは、
- 経営者の7割が学び直しに前向き
- 学び直しの内容は経営実務に直結するテーマが中心
- 効果は経営改善から従業員育成まで幅広く及ぶ
- 課題は「時間」「費用」「必要性の認識不足」
- 学び直しを実践する経営者は企業の成長にもつながっている
という実態です。
経営者の学び直しは、単なる自己啓発にとどまらず、企業経営そのものを変える大きな力を持っています。中小企業においては、限られた資源の中で効率的に取り組む必要がありますが、国や自治体、支援機関の施策を上手に活用しながら、一歩を踏み出すことが重要です。
東京商工会議所 経営者の学び直しに関するアンケート調査