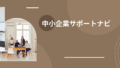2025年(令和7年度)も、国が中小企業の官公需受注機会を拡大するための方針を閣議決定しました。その名も「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」。
一見すると堅い行政文書に見えるこの方針ですが、実は中小企業にとって「売上を安定させるチャンス」や「新しい市場開拓の糸口」になり得るものです。本記事では、専門用語をできる限り噛み砕きながら、今回の方針のポイントをわかりやすく解説します。
官公需とは?そして、なぜ注目すべきなのか?
「官公需(かんこうじゅ)」とは、国や自治体などが発注する物品や役務(サービス)を指します。官公需契約の特徴は、以下のように中小企業にとって魅力的です。
- 支払いの確実性が高い
- 安定した受注につながる
- 実績づくりに最適
令和7年度の方針では、これらの官公需を「より多くの中小企業へ」分配することを大きな目標に掲げています。
中小企業向け契約比率「61%以上」を維持へ
今回の基本方針では、国の契約において「中小企業・小規模事業者向けの契約比率を61%以上にする」という数値目標が明示されています。金額にして約5兆9,193億円規模です。
さらに、新規中小企業者(これまで国との取引実績がない企業)についても、3%以上の契約比率を維持・拡大するという明確な方針が示されました。
つまり、これから官公需に挑戦したい中小企業にとっても、大きなチャンスが広がっているのです。
価格転嫁と賃上げを官公需で後押し
近年の課題として、中小企業は原材料費や人件費の高騰に悩まされ続けています。そのコスト増加分を「きちんと価格に反映できるか」が利益を左右します。
今回の方針では、官公需の契約においても価格転嫁を正当に行えるよう、次のような配慮が明記されています。
- 最低賃金の引き上げを考慮した契約条件の設定
- 労務費・エネルギー費などの上昇に伴う契約金額の見直し
- 契約前・後の段階での価格改定の柔軟な運用
これにより、「値上げをしたいけど言い出せない」という中小企業の声に応える体制が整備されています。
情報公開と相談窓口の拡充で透明性アップ
官公需と聞くと、「情報が不透明」「入札の仕組みが分かりにくい」といったイメージを抱かれる方も多いかもしれません。
令和7年度はこの点にも大きな改善が図られます。
- 各省庁の契約情報をポータルサイトで一元化
- 入札仕様や発注条件を明記した仕様書の整備
- 各機関に官公需専用の相談窓口を設置
これにより、特に初めての企業でも必要な情報にアクセスしやすくなり、安心して官公需に参加できるようになります。
新規企業やスタートアップの参入を歓迎

今回の方針で特に強調されているのが、「新規中小企業者」や「スタートアップ」への支援です。
- 実績を求めすぎない入札要件の緩和
- 新製品や独自技術を持つ企業への随意契約の活用
- トライアル発注制度の活用促進
これにより、創業して間もない企業や、イノベーションを起こすベンチャー企業にも門戸が開かれています。
分割発注・納期平準化で柔軟に対応
多くの中小企業にとって、大型案件を一括で受注するのはハードルが高いものです。そうした声に応える形で、今回の方針には次のような具体策が盛り込まれています。
- 大規模案件を細かく分割して発注
- 納品回数の集約や配送時間帯の配慮
- 契約書に柔軟な納期変更や価格改定の条項を明記
こうした施策により、「少しずつ・できる範囲で」官公需に関わることができるようになります。
地域経済・被災地支援への明確な配慮
地域経済や災害からの復興支援も、この方針の柱の一つです。
- 被災地域の事業者へ優先的な契約
- 災害時の供給体制を担う企業との協定促進
- 地元の燃料供給や建設事業への随意契約を検討
地域に根ざした中小企業が安定的にビジネスを継続できるよう、国として積極的に支援していく姿勢が打ち出されています。
まとめ|チャンスは待つものではなく“掴む”もの
令和7年度「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」は、単なる行政方針ではありません。そこには、これまで官公需と縁がなかった企業にも大きなチャンスが広がっています。
要点を振り返ると――
- 官公需契約の61%を中小企業へ
- 新規中小企業者の受注機会も3%以上に
- 情報の透明化と相談体制の整備
- 賃上げや原材料費の転嫁を支援
- 地域企業・被災地域企業への手厚い配慮
中小企業の皆さんにとって、官公需は「信用と成長」を両立できる市場です。これを機に、ぜひ一度チャレンジを検討してみてください。