近年、中小企業にとって「イノベーションの創出」は生き残りをかけた最重要課題となっています。しかしながら、研究機関との連携をどのように始めれば良いか分からない、大学との接点が見つけられない、といった声も数多く聞かれます。
そこで今回ご紹介するのが、令和7年度 地域の産業活性化を加速する「産学連携前に共に議論し合う場」事業です。関東経済産業局が主導するこの事業は、産学連携の“前段階”に焦点を当て、中堅・中小企業の研究開発や新製品開発に向けた課題の明確化をサポートする革新的な取り組みです。
この記事では、本事業の仕組み、対象企業、メリット、応募方法、スケジュールなどを徹底解説します。中小企業診断士の視点から、実務に活かせるよう噛み砕いて解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ今、「議論の場」が必要なのか?―課題の“前処理”がイノベーションを生む
地域経済を支える中小企業が新たな価値創出を目指すには、大学等との連携による研究開発が鍵となります。しかし、次のような“初期の壁”に直面していませんか?
- 「そもそもどんな技術が必要かが分からない」
- 「大学に相談したいが、どう話を持ちかけてよいか分からない」
- 「自社の技術にどんな応用可能性があるのか客観的に評価してほしい」
このように、“連携以前”の段階で立ち止まってしまっているケースが非常に多いのが現状です。
本事業は、そうした初期フェーズの悩みを解消するため、企業の課題や技術の棚卸しを行い、複数の大学と議論する機会を提供することで、イノベーションの土台づくりを後押しします。
事業の目的と背景 ― 地域のイノベーション創出の加速
この「共に議論し合う場」事業は、次のような目的で設計されています。
- 地域企業の研究開発・新製品開発の上流フェーズにおける技術的課題の明確化
- 連携候補先の大学や研究機関との接点の創出
- 地域企業と大学等とのネットワーク構築支援
- 結果として、地域経済の持続的発展と競争力向上を実現
対象となるのは、関東経済産業局管内(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)の中小企業および中堅企業です。
本事業のポイント ― 3ステップで“連携前段階”を支援
この事業の最大の特徴は、産学連携の「準備段階」に徹底的に寄り添うことです。支援は以下の3ステップに分かれ、各段階で専門アドバイザのサポートを受けられます。
事前ヒアリング(所要時間:約2時間)
企業の現状、新規事業構想、技術的課題などについて、アドバイザが丁寧にヒアリング。自社の強みや連携の方向性を一緒に整理します。
相談内容の整理会(所要時間:約3時間)
関係機関やアドバイザとともに、大学に相談すべき技術課題・目的を具体化。初対面の大学担当者ともスムーズに話せるよう、議論の土台を作ります。
複数大学とのディスカッション(所要時間:約2時間)
大学(3機関程度)とのディスカッションを実施。相互に質問・意見交換しながら、連携候補や方向性を探ります。アドバイザがファシリテーターとして議論を活性化します。
アドバイザによる支援が強力
アドバイザは、産学連携の専門家だけでなく、技術分野の知見を持つ実務家が担当。単なるコーディネーターではなく、課題の本質を掘り下げる“伴走者”として企業を支えます。
また、関東経済産業局とEYストラテジー・アンド・コンサルティングが事務局として運営。国の支援として安心して活用できる仕組みになっています。
応募対象企業と条件
この事業に応募できるのは、以下の要件を満たす企業です。
【対象エリア】
関東経済産業局管内(茨城県〜静岡県)のいずれかに本社が所在
【企業規模】
中小企業基本法で定義された中小企業または中堅企業(従業員2000人以下)
【応募条件(抜粋)】
- 研究・技術開発に基づく新規事業や新製品に取り組む意思があること
- 経営層と開発担当者の両者が本事業に参加可能であること
- ヒアリングやディスカッション等に積極的に時間を割けること
- 成果報告や事後のアンケートに協力できること
募集スケジュールと採択数
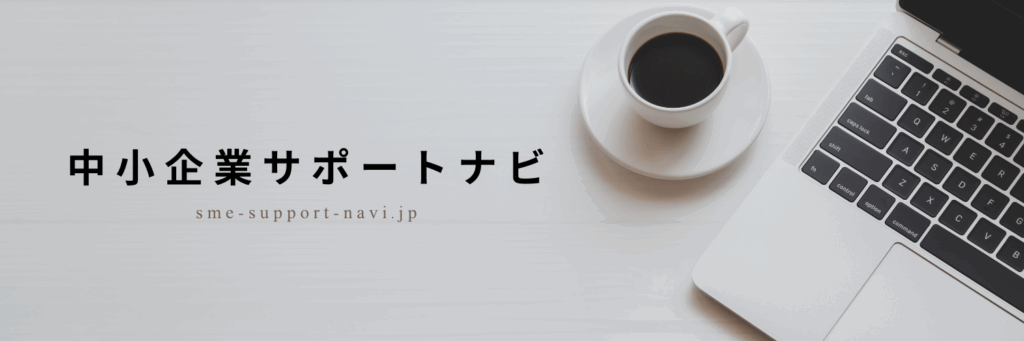
この事業は年2回の募集を予定しています。
- 【第1期】募集期間:2025年8月1日(金)~8月29日(金)
- 【第2期】募集期間:2025年10月上旬~下旬(予定)
- 採択予定:合計で7社程度
各期ともに3~4ヶ月のプログラムとなります。応募多数が予想されますので、関心のある企業は早めの準備がおすすめです。
審査方法と基準
書面審査により採択企業が決定されます。審査では以下のような観点が重視されます。
【必須評価項目】
- 産学連携による課題解決ニーズが明確であること
- 新規事業における研究シーズ探索への意欲があること
- 社内体制の整備状況
- 地域経済や業界の課題解決に資する内容
【加点要素】
- 新規事業の成長可能性
- 既に支援機関との相談実績がある
- 社会課題や業界課題への貢献度
本事業を活用すべき企業像とは?
この事業が特にフィットするのは、以下のような企業です。
- 自社の技術を他分野へ展開したいが、専門家の目で整理したい
- 「新製品を開発したいが、大学との接点がない」
- 「既存の製品をアップグレードしたいが技術的な壁がある」
- 「研究者との協業を試してみたいが、まずは議論から始めたい」
産学連携は、始めの一歩が最も難しいとも言われます。このプログラムでは、その「最初の壁」を専門家とともに突破できる仕組みが整っています。
よくある質問(FAQ)
Q:ディスカッションは対面ですか?オンラインですか?
A:企業の状況に応じて柔軟に対応。原則はオンラインですが、必要に応じて対面の場を設ける場合もあります。
Q:大学側の専門性は選べますか?
A:企業の課題に応じて、最適な大学(3機関程度)が選定されます。事務局・アドバイザが適切にマッチングします。
Q:自社の守秘情報は守られますか?
A:もちろんです。公開不可の情報は明示していただき、議論はあくまで共有可能な範囲で行われます。
応募方法
応募はメールでの提出となります。
提出先メールアドレス:
📧 sangaku.office@jp.ey.com
(件名:「産学連携前に共に議論し合う場事業応募書類」)
提出期限(第1期):2025年8月29日(金)
応募様式(申込書)は、以下の公式ページよりダウンロード可能です:
🔗 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/r7fy_jigyou_koubo.html
まとめ ― 産学連携の“準備”を支援する国の新たな挑戦
本事業は、従来の「連携ありき」の制度とは一線を画し、企業が連携に至る前段階を丁寧にサポートする、実践的かつ現場目線の支援策です。
これまで大学との連携に「縁がなかった」「難しそう」と感じていた中小企業にも、大きなチャンスとなるでしょう。
次なる成長戦略を描くうえで、産学連携を取り入れたいと考える経営者・支援者の皆さま。ぜひこの機会に、「議論の場」を足がかりに未来への一歩を踏み出してみてください。
📩 お問い合わせ先
事務局:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
担当者:中山・柏木・土屋
Email:sangaku.office@jp.ey.com



