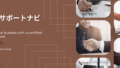中小企業が直面する最大の課題のひとつが「人材の確保と定着」です。特に若手人材の採用後、3年以内に離職してしまうケースは少なくありません。背景には、待遇面の不満や職場環境への不安、成長実感の欠如などが複合的に存在しています。
そうした中、東京都が令和7年度(2025年度)に実施するのが「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」です。この制度は、社員満足度の向上を目的とした福利厚生の取り組みに対して助成を行うもので、企業の人材戦略を後押しする実践的な施策といえます。助成金の支給申請前には、専門家派遣(最大3回)を利用しながら取組計画書を作成する点が特徴です。
この記事では、令和7年度の最新公募要領に基づき、助成金の目的・対象事業・申請方法・審査内容までを分かりやすく解説します。経営者・人事担当者・中小企業支援者の皆様にとって、有益な情報を網羅的にお届けします。
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金https://www.es-koujou.jp/about/
事業目的|社員満足度(ES)向上による若手人材の定着支援
本助成金は、東京都内の中小企業等における「若手人材(35歳未満)」の確保・定着を目的として、福利厚生の充実による社員満足度(ES)の向上を図るものです。人材の流出を防ぎ、働きやすく活力ある職場環境を実現することで、地域経済の持続的成長につなげる狙いがあります。
近年、採用だけでなく“働き続けてもらうための仕組み”の整備が重要視されています。給与だけでなく、住宅・食事・健康面などの支援も重要な要素となっており、ES向上が離職防止に直結することは各種調査でも明らかです。中小企業にとっては、限られた資源の中でこうした環境を整備するための一助として、本助成金が設計されています。
事業内容|対象事業・助成対象者・助成率・助成額・対象経費・実施主体
助成対象事業
以下の3つの取り組みのうち、2つ以上を組み合わせて新たに導入・整備することが条件です。
- 住宅の借り上げ
従業員用の社宅などを新たに借り上げて提供する取り組み - 食事等の提供
弁当の支給、社員食堂の導入、飲料提供などの定期的な食事支援 - 健康増進サービスの提供
健康診断、健康器具の導入、ウェルネスプログラムなどの提供
助成対象者(企業の要件)
本助成金を申請できるのは主に以下の条件を満たす中小企業等です(詳細は募集要項を参照)
- 都内に本社又は事業所があること
- 中小企業等であること
- 都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者である者を1人以上、6カ月以上継続して雇用していること
- 常時使用する従業員の総数に占める常時使用する若手(35歳未満)従業員の割合が30%以下であること
- 過去3年間の常時使用する若手(35歳未満)従業員の合計採用数が、常時使用する従業員の総数の10%以下であること
- 過去1年以内に若手人材を含む求人活動を行っていること
助成率と助成額
- 助成率:1/2(50%)
- 助成限度額:
- 住宅の借上げ:200万円(1戸あたり月82,000円を上限とし、その半額41,000円までが助成対象)
- 食事提供:50万円
- 健康増進サービス:50万円
- 合計最大助成額:300万円
助成対象経費(概要)
- 住宅の賃料(契約書・領収書のあるもの)
- 弁当提供費、社員食堂の設置・運営費
- 健康診断費、設備費、講師謝金、機材導入費など
スケジュール|支援申込受付期間と募集企業数(先着順)
この助成金の特徴の一つは、前期・後期に分かれた申込期間が設けられていることです。申請はJグランツ(電子申請システム)または郵送で、受付は先着順です。
前期
- 申請期間:令和7年5月12日(月)~令和7年8月8日(金)
- 募集企業数:30社
後期
- 申請期間:令和7年8月18日(月)~令和7年11月14日(金)
- 募集企業数:30社
各期間とも、最終日23時59分までに申請を完了することが条件です。書類不備があると再提出が求められ、その間に募集枠が埋まる可能性もあるため、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。
助成対象事業の詳細|ES向上につながる3つの取り組み
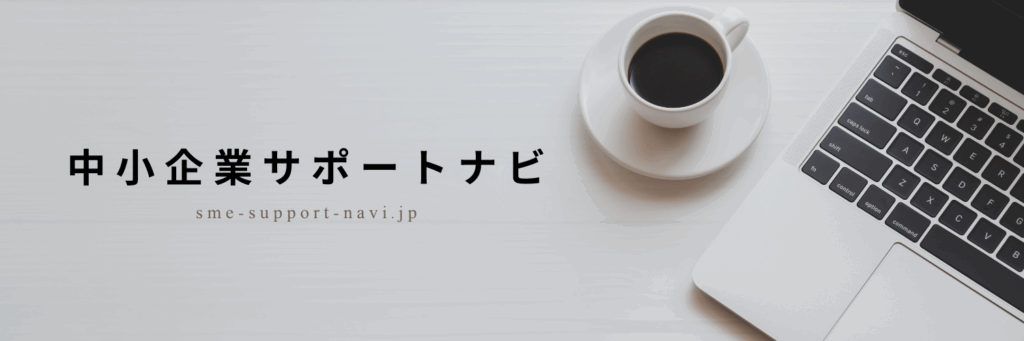
本助成金は、社員満足度(ES)向上のために具体的に整備する3つの施策に対し、2つ以上を実施することが要件とされています。それぞれの取り組みの実施内容は以下の通りです。
住宅の借上げ
住宅の借上げは、若手社員に社宅等を提供し、生活の安定や通勤負担の軽減を図ることで定着促進を目指す施策です。
- 対象は都内の共同住宅に限られます(戸建ては不可)
- 企業が貸主と直接契約し、従業員に転貸(社宅提供)する形式
- 月額家賃の1/2(最大41,000円/戸)を助成
- 助成期間は交付決定日から最長で令和8年3月31日まで
なお、交付決定前に契約・入居済の社宅は対象外であり、必ず決定後に新たに契約・提供することが必要です。
食事等の提供
若手社員を中心に、健康と満足度向上を目的とした食事支援も助成対象となります。
- 弁当配布、ケータリング、設置型社員食堂、ウォーターサーバーの導入等が対象
- 継続的な提供であることが必要(単発イベントは不可)
- 対象従業員に無償または補助付きで提供される形式
- 助成対象経費の1/2(最大50万円)
福利厚生としての食事支援は、ES向上への効果が高いだけでなく、健康維持や職場内コミュニケーションの活性化にも寄与します。
健康増進サービスの提供
社員の健康づくりに資するサービスの導入も、ES向上に欠かせない要素です。
- 健康診断・ストレスチェック・健康指導・メンタルヘルスセミナー
- マッサージチェアの設置、簡易ジム設備の導入など
- フィットネスジム利用補助や健康アプリの利用も対象
- 経費の1/2(最大50万円)を助成
「働きやすい職場」には、健康面での支援体制が不可欠であるという考えのもと、幅広い施策が対象となっています。
助成対象経費の詳細|経費要件と除外項目
助成対象となる経費は、原則として以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 助成対象事業に直接必要な経費であること
- 契約・支出・導入等が交付決定後に行われていること
- 見積書・契約書・領収書等によって支出が証明可能であること
経費例(対象となるもの)
- 賃貸住宅の家賃(住宅借上げ)
- 弁当提供サービスの月額利用料
- 健康診断費用、健康機器の購入費
- セミナー講師への謝金、資料印刷費
対象外経費
- 汎用的な備品・什器の購入(例:椅子、机など)
- 自社運営による食堂の人件費や食材購入費
- 福利厚生としての飲酒・娯楽目的の支出
- 助成金交付決定前に発注・契約・支払いが行われた経費
いずれも、助成金の性質上「明確に事業目的に即した支出」でなければ対象とはなりません。証憑書類の整備が不可欠であるため、実施前にしっかりと確認しておくことが重要です。
専門家と相談(取組計画作成)
助成金の支給申請前には、事務局から派遣された専門家が都内事業所を直接訪問して、支援決定事業者との相談を最大3回行います。
専門家との相談では、社内における若手人材の採用・定着や社員満足度に関する課題の把握を行った上で、それを踏まえて助成対象事業を含む社員満足度向上のための取組計画を作成します。
申請方法|Jグランツを使った電子申請又は郵送による申請、提出書類
本助成金は、Jグランツ(国の電子申請システム)を利用した電子申請または郵送による申請となっています。
申請に必要な主な書類
- 支援申込書(様式1)
- 実施計画書(様式2)
- 企業概要書
- 就業規則、給与規程等の写し
- 対象施策にかかる契約書・見積書(予定先含む)
- 若手社員の在籍確認書類(名簿・年齢確認)
申請にあたっては、提出書類が非常に多岐にわたるため、チェックリストを活用して確実に揃えることが求められます。また、計画書の記載内容が不十分であったり、助成目的との乖離がある場合には差し戻しや不採択の対象となります。
審査方法|書類審査と支援決定のポイント
本事業は、先着順による書類審査方式で支援企業が決定されます。申請が早ければ必ず通るというわけではなく、書類の内容・整合性も重要視されます。
審査で重視されるポイント
- 申請内容が制度目的に適しているか(ES向上→若手定着)
- 計画の具体性、実施可能性、継続性があるか
- 経費の使途が合理的かつ明確に説明されているか
- 必要書類の整合性(例:契約先との関係、見積妥当性)
- 法令遵守・雇用環境の健全性
書類に不備があると差し戻しとなり、結果的に支援対象から漏れる可能性があります。申請後は書類の再提出やヒアリングの連絡がある場合もありますので、迅速に対応できる体制を整えておくことが望ましいです。
まとめ|若手人材の定着は「満足度」から。戦略的福利厚生で企業力アップ
ES(社員満足度)の向上は、単なる福利厚生ではありません。従業員が働く職場を「自分にとっての居場所」と感じ、長く活躍してくれる基盤をつくる経営戦略の一部です。
今回ご紹介した「ES向上による若手人材確保・定着事業助成金」は、そんな企業の姿勢を支える東京都の支援制度です。
- 採用した若手社員の定着率が低い
- 福利厚生を整備したいが、コストが心配
- 職場環境の改善を計画的に進めたい
という企業様にとっては、実に使い勝手のよい制度といえるでしょう。申請から実施、報告までには一定の事務手続きが必要ですが、支援を受けることで大きな成果を得ることが可能です。
申請を検討される際には必ず募集要項をご確認の上、ご不明な点は事務局、専門家へご確認下さい。
募集要項(電子申請)https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_0601.files/070417_ESboshuyoko_densi.pdf