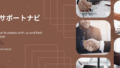医療機器の分野は、今や「ものづくり中小企業」にとっても新たな成長のチャンスとして注目を集めています。とはいえ、医療機器の開発や販売には厳格な法規制や専門的な知識、医療現場との密接な連携が求められるため、参入障壁が高いことも事実です。
そこで東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が展開するのが、「医療機器等事業化支援助成事業」です。本記事では、第22回の募集要項に基づき、事業の目的、助成内容、対象企業、申請スケジュール、申請手順まで詳しく解説します。
医療機器等事業化支援助成事業https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html
事業目的
本事業は、都内のものづくり中小企業が医療機器産業へスムーズに参入できるよう支援するために設けられています。
医療機器はニッチな市場が多く、品目数は30万を超える一方で、大手企業が研究開発に乗り出さない分野も多々あります。そうした空白領域こそ、中小企業にとってのビジネスチャンス。しかし、薬機法による規制や許認可の壁、医療機関との信頼関係構築が大きなハードルとなっています。
この助成金制度は、都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等との連携体制をもとに、医療機器開発の現場における具体的な製品化に向けた開発費の一部を助成し、参入支援を行うものです。
事業内容
助成対象者
本助成事業の対象となるのは、以下のいずれかに該当する企業です。
- 都内で事業を営む中小ものづくり企業
- 都内で法人登記(本社・支店可)されている医療機器製販企業
- いずれの企業も、医療機器産業参入支援事業または東京都医工連携HUB機構への会員登録が必須です。
加えて、申請者は、申請時点で開発の主たる部分を担う都内中小企業を含む「連携体(2社以上)」を組成する必要があります。
助成対象事業
次の2点を満たす事業が対象となります。
- 都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携して医療機器の開発または上市を目的としていること。
- 臨床ニーズ(病院、診療所など)に基づいた開発であること。
なお、助成対象外となる事業には、すでに収益化されているもの、量産段階に入っているもの、開業資金や設備導入のみを目的とした事業などが含まれます。
助成額・助成率・助成期間
- 助成額上限:5,000万円(下限500万円)
- 助成率:2/3以内(残り1/3は自己負担)
- 助成期間:交付決定日(令和8年3月1日予定)から令和13年2月28日までの最長5年間
なお、過去に同事業に採択され助成金を受領している場合、その受領額を差し引いた額が今回の上限額となります。
助成対象経費
医療機器の開発に直接関わる経費が対象です。以下に該当する条件を満たす必要があります。
- 令和8年3月1日〜令和13年2月28日までに契約・発注・支払が完了していること
- 助成対象事業にのみ使用され、明確に区分できること
- 所有権が助成事業者に帰属するもの
具体的な経費区分は、開発費・人件費・外注費・設備費などが含まれます。
助成事業のスケジュール

申請から採択、事業実施までの全体の流れは以下の通りです。
- 事前ヒアリング予約:令和7年7月23日(水)〜9月8日(月)
- 事前ヒアリング実施:令和7年7月31日(木)〜9月16日(火)
- 申請書提出期間:令和7年9月17日(水)〜10月1日(水)
- 対面受付:令和7年10月29日(水)〜11月11日(火)
- 一次審査(書類審査):10月〜11月
- 現地調査:11月下旬〜12月中旬
- 二次審査(面接審査):令和8年1月8日〜16日の間
- 交付決定通知:令和8年2月下旬
- 助成事業開始:令和8年3月1日〜
助成対象事業の詳細
この助成制度は、ただお金を出すだけではなく、「ハンズオン支援」も行われます。これは、プロジェクトマネージャーが経営・技術・知財・販路開拓などの観点から中小企業に対してきめ細やかな支援を提供するものです。
また、申請時には、「製品の完成」または「試作品の完成」のどちらかを達成目標として設定し、それに基づいた進捗管理が行われます。
連携体の形成が必須条件であるため、企業間連携の設計や役割分担を早期に明確化することが、採択への鍵となります。
助成対象経費の詳細
助成対象となる経費は、「開発に直接関連する費用」であり、具体的には以下が該当します。
- 原材料や副資材費
- 設備の設計・製作・改良費
- 専門家への外注費
- 製品試作にかかる人件費
- 試験・評価にかかる経費
- 知財関連の取得・登録にかかる費用
いずれの経費も、明確に本事業に帰属することが必要であり、帳票・証拠資料として確認可能な形で管理することが求められます。
申請方法等
申請には以下の準備が必要です。
- gBizIDプライムの取得(jGrantsを利用)
- 医療機器産業参入支援事業または東京都医工連携HUB機構への会員登録
- 事前ヒアリングの受講
- 必要書類のダウンロード・記入・提出
申請は電子申請システム「jGrants」から行い、記入例や必要書類は公社ホームページに掲載されています(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html)。
審査方法
審査は以下の3段階で構成されます。
- 一次審査(書類審査)
- 現地調査
- 二次審査(面接)
評価の観点は次の通りです。
- 技術的優秀性、市場性、実現性
- 本事業の目的との整合性
- 経営の健全性(財務状況など)
審査は非公開で行われ、結果は書面で通知されます。審査通過後も、助成金交付額は申請額と異なる場合がありますので、予算には一定の余裕を持って臨むことが望まれます。
まとめ:今こそ医療機器市場への一歩を
「医療機器等事業化支援助成事業」は、単なる資金援助にとどまらず、中小企業が医療分野へ新たに踏み出すための強力な後押しとなる制度です。
医療分野は少子高齢化が進む日本において、今後も成長が期待される分野であり、高度な製造技術や独自性のある開発力を持つ企業にとっては大きなビジネスチャンスが眠っています。
ぜひこの機会に、制度の詳細を理解し、採択を目指してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
申請を検討される際には募集要項をご確認の上、ご不明な点は事務局等をご確認下さい。
募集要項https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/rmepal0000000ec2-att/22th_jigyouka_youkou.pdf