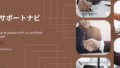令和7年8月8日、独立行政法人中小企業基盤整備機構から「中小企業省力化投資補助金(一般型)」第2回公募の採択結果が公表されました。全国から707件もの事業が採択され、その取り組み内容や導入設備は多岐にわたります。
本記事では、採択結果の概要に加え、実際に採択された事例を3件紹介し、さらに採択事業計画名から見える傾向を分析します。
採択結果の全体像
今回の採択では、業種別では製造業(58.4%)が圧倒的多数を占め、次いで建設業(12.4%)、卸売業(6.8%)と続きます。
都道府県別では、大阪府(67件)、愛知県(66件)、東京都(63件)が上位を占め、全国的にバランスよく採択が行われた一方、地域の産業構造による偏りも見られました。
補助金申請額の分布を見ると、1,500万円以上〜1,750万円未満が最も多く、中小企業が一度に大きな設備投資を行う事例が目立ちます。また、従業員規模では6〜10名の企業が最も多く、少人数でも省力化による効果を最大化しようという姿勢が読み取れます。
採択事例① 製造業:熟練技能の自動化で生産性と品質を両立
ある創業100年以上の老舗メーカーでは、熟練作業者による手縫い針製造が主力事業でした。しかし熟練者と非熟練者では作業時間に5倍の差があり、年間1,500時間以上の効率損失が発生していました。加えて、高齢化による技能承継の課題も迫っていました。
そこで、省力化機器としてワイヤ放電加工機とロータリーテーブルを導入。これにより、
- 作業全体の約80%を効率化
- 製造数量を70%増加
- 微細加工による高付加価値製品の開発が可能に
さらに、削減された作業時間を新製品開発や顧客ヒアリングに充てることで、売上拡大の好循環を生み出す計画です。
採択事例② 建設業:重機の高度化で人手不足を解消
ある建設業者では、現行の重機にチルトローテーターがなく、作業のたびにアタッチメントを交換する非効率な状況でした。これにより、年間約1,200時間の余分な労働と1,500万円のコスト増が発生していました。
そこで、油圧ショベルにチルトローテーターや各種バケットを組み合わせて導入。結果として、
- 作業時間を45%削減
- 創出時間を営業・新事業開発へ再配分
- 若手育成や高精度施工の体制構築
これにより、より高単価・高利益率の案件受注を狙える経営基盤が整備されました。
採択事例③ 卸売業:物流センターのDX化で出荷精度を向上
ある卸売業者では、多品種少量の受注を紙伝票で処理しており、1日400件の出荷に50時間・230kmの移動を要し、ピッキングミスも約2%発生していました。
ここで導入されたのがピッキングカートシステムとタブレットピッキングシステムです。
- 年間労働時間を5,000時間削減
- 移動距離を2万km削減
- ピッキングミス率を1%未満に低減
- 在庫管理の最適化とコスト削減を実現
これにより、従業員負担の軽減と顧客満足度の向上を同時に達成しています。
採択事業計画名から見える特徴的な傾向

707件の事業計画名を俯瞰すると、以下の傾向が明らかです。
- 自動化・ロボット化
「溶接ロボット導入」「自動包装機」「AI検査機」など、作業の完全自動化を目指す案件が多数。 - DX・デジタル化
「基幹システム構築」「営業DX」「クラウド管理システム」など、業務フローのデジタル変革が進行。 - 高付加価値化
「ブランド米販路拡大」「高精度部品製造」「海外展開強化」など、付加価値向上と新市場開拓を狙う動き。 - 人手不足対応
特に地方や建設業で「人員削減・再配置」を目的とした省力化投資が目立つ。 - 環境・サステナビリティ対応
「環境配慮型製品」「CO2削減」「再生資源活用」といったESG要素を盛り込む事例も増加傾向。
成功のカギは「省力化+価値創造」
今回の採択結果から見えてくるのは、単なる省人化ではなく、削減したリソースを新しい価値創造に振り向ける戦略が高く評価されている点です。
例えば製造業の事例では、機械導入で生まれた時間を新製品開発に充てる。建設業では営業・高精度施工に再配分する。卸売業では在庫管理とマーケティング精度を上げる——いずれも「省力化の先」を見据えています。
補助金活用を検討している企業は、「何を効率化するか」だけでなく、「効率化で得た時間・人員で何を生み出すか」を明確にすることが重要です。
まとめ
- 採択の過半数は製造業で、次いで建設業・卸売業が多い。
- 採択事例は、熟練技能の自動化、重機高度化による施工効率化、物流DX化など多様。
- 事業計画名からは「自動化」「DX化」「高付加価値化」「人手不足対応」「環境配慮」が主要テーマとして浮かび上がる。
- 成功の鍵は「省力化」と「価値創造」の両立にある。
本補助金は、単なる作業削減ではなく、企業の成長戦略を後押しする強力な武器になり得ます。次回以降の公募に向けて、自社の課題と成長ビジョンを明確に描くことが、採択への近道となるでしょう。