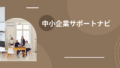2025年8月に帝国データバンクが公表した「価格転嫁に関する実態調査」によれば、日本企業の価格転嫁率は 39.4% にとどまり、調査開始以来最低を記録しました。つまり、コストが100円上昇しても販売価格に反映できるのはわずか39円程度であり、残りの6割超を企業が自らの収益で負担しているのが現状です。
この調査は全国26,196社を対象に行われ、1万626社から有効回答を得た大規模調査です。その結果は、中小企業経営者や支援者にとって看過できない厳しい実態を示しています。
本記事では、この調査結果の詳細を解説するとともに、なぜ価格転嫁が進まないのか、その背景を整理します。さらに、中小企業が活用できる「価格転嫁サポートツール」などの支援策についてもご紹介します。
価格転嫁率の現状:39.4%にとどまる実態
部分的な価格転嫁にとどまる企業が多数
回答企業の73.7%が「多少なりとも価格転嫁できている」と答えていますが、内訳をみると多くは「2割未満」「5割未満」にとどまっています。完全に価格転嫁できている企業(100%転嫁)はわずか3.8%にすぎません。
一方で「全く転嫁できていない」と回答した企業も12.5%に達し、約8社に1社はコスト増を完全に自己負担している実態が明らかになりました。
コスト項目別の価格転嫁率
- 原材料費:48.2%
- 人件費:32.0%
- 物流費:35.1%
- エネルギーコスト:30.0%
原材料費は比較的転嫁が進んでいますが、人件費や物流費、エネルギー費は3割前後と低迷しており、中小企業に大きな負担となっています。
なぜ価格転嫁が進まないのか
消費者の抵抗感と競争の激化
飲食店や旅館・ホテルといった川下産業では、消費者の節約志向が強く、「値上げすれば客足が遠のくのでは」という懸念が根強くあります。結果として、転嫁率は飲食店で32.3%、旅館・ホテルで24.9%と低水準です。
説明が難しいコストの存在
製造業の声として「原材料費は根拠を示せるが、人件費や物流費は説明が難しい」という意見が寄せられています。顧客に納得してもらうのが難しく、十分な価格転嫁につながらないのです。
制度・契約上の制約
医療・福祉業界では診療報酬や介護報酬による価格制約、出版業界では再販売価格維持制度、不動産業界では手数料規制があり、自由な価格改定ができません。さらに、フランチャイズ契約や市場取引に依存する業種でも、価格決定権の制約が大きく、価格転嫁が困難です。
中小企業が取るべき価格転嫁戦略

コスト上昇の根拠を明確に伝える
取引先や消費者に対して「なぜ値上げが必要なのか」を誠実に説明することが第一歩です。調査でも「正確に状況を伝え、理解いただける先との取引を重視している」と答える企業がありました。透明性を高めることで信頼関係を築くことができます。
付加価値を高めた価格改定
単なる値上げではなく、品質改善やサービス向上と組み合わせることで「価格改定=価値向上」と認識されやすくなります。たとえば飲食業では「国産食材の使用」「環境配慮型の取り組み」を同時に打ち出すことで、消費者の納得感を得やすくなります。
支援策の積極活用
中小企業が単独で価格交渉を行うのは難しいケースも多くあります。こうしたときに活用すべきが、国や自治体の支援策です。
経済産業省、中小企業庁等の施策の活用法
経済産業省・中小企業庁は、価格転嫁を後押しするために価格転嫁検討ツールなどを提供しています。
価格交渉の必要性の検討等
- 価格転嫁検討ツール:簡単な操作で、商品別(取引先別)の収支状況が把握でき、価格転嫁の必要性が分かるツール https://kakakutenka.smrj.go.jp/kakakukentou/index.html
- 儲かる経営 キヅク君:商品・取引先ごとの収支状況やコスト構造の変化を可視化し、価格転嫁の目安や商品戦略、事業戦略等を検討することができるシミュレーションツール https://kakakutenka.smrj.go.jp/moukaru/index.html
- 中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック:取引先と価格交渉を行うために準備しておくとよいツールや、交渉を行う上で押さえておくとよいポイントをまとめたハンドブックhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/kakaku_kosho_handbook.pdf
関連する制度的支援
- パートナーシップ構築宣言:大企業と中小企業が対等な取引を行うための枠組み
- 価格交渉促進月間:業界全体で価格交渉を後押しするキャンペーン
- 専門家相談窓口:中小企業診断士や商工会議所での無料相談
これらを組み合わせることで、交渉の下支えとなり、中小企業が適正な価格転嫁を実現しやすくなります。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shien_tool.html
今後の展望とまとめ
今回の調査で明らかになったのは、日本企業の価格転嫁が頭打ちになりつつある現実です。
- 価格転嫁率は39.4%と過去最低
- 川下産業ほど価格転嫁が困難
- 制度や契約上の制約で自由に価格改定できない業界が存在
このままでは、中小企業の収益力低下が賃上げや投資の停滞につながり、日本経済全体の成長にブレーキをかけかねません。
だからこそ、中小企業にとっては以下の3点が重要です。
- コスト上昇の根拠を丁寧に説明すること
- 値上げを「付加価値向上」と組み合わせて行うこと
- 経済産業省や自治体等の支援策やツールを積極的に活用すること
価格転嫁は単なるコストの押し付けではなく、企業の持続可能性を守るための正当な経営判断です。国の支援策を活用しながら、取引先や消費者との信頼関係を築き、適正な価格交渉を進めていくことが、これからの中小企業経営に不可欠と言えるでしょう。