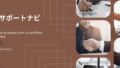東京都が実施する「令和7年度 製品改良/規格適合・認証取得支援事業」は、製品の改良や国際規格への適合・認証取得を支援する助成金制度です。自社製品の機能強化やISO・CEマーキング取得などを検討している中小企業にとって、非常に大きな後押しとなる仕組みです。
この記事では、事業の目的から助成内容、スケジュール、対象経費、申請方法、審査の流れ、そして過去採択企業の傾向まで、制度のポイントを分かりやすく解説します。
事業目的
本助成事業の目的は、都内中小企業が製品改良や規格適合・認証取得を通じて国内外での販路開拓を実現し、経営力を強化することです。
例えば、輸出を目指す企業にとってはCEマークやISO規格の取得が必須条件となることが多く、また国内市場でも品質や安全性の裏付けとなる認証を取得することで、取引先からの信頼性向上に直結します。
単なる技術開発ではなく、実際の市場展開や販路開拓に直結する活動を助成している点が特徴です。
助成内容(助成対象者・助成額・助成率・期間など)
助成は大きく分けて3つの申請区分があります。
製品改良プロジェクト
- 対象:自社開発製品(試作品含む)の改良
- 内容:機能追加、性能向上、試験評価、実証データ取得など
- 助成限度額:500万円(下限額50万円)
- 助成率:2分の1以内
- 助成対象期間:令和8年3月1日~令和9年11月30日(最長1年9か月)
規格適合・認証取得プロジェクト(製品改良目標なし)
- 対象:国内外規格の適合性評価・認証取得(ISO、CEマーキングなど)
- 助成限度額:500万円
- 助成率:2分の1以内
- 助成対象期間:令和8年3月1日~令和9年11月30日(最長1年9か月)
規格適合・認証取得プロジェクト(製品改良目標あり)
- 対象:規格取得に加え、市場ニーズ対応のための製品改良も実施する事業
- 助成限度額:500万円
- 助成率:2分の1以内
- 助成対象期間:令和8年3月1日~令和10年11月30日(最長2年9か月)
- 特徴:製品改良費と規格認証費の両方が対象となり、長期間にわたる支援が可能
助成事業のスケジュール
本事業は電子申請(Jグランツ)限定で受付され、以下の流れで進行します。
- 申請受付期間:令和7年10月17日(金)~10月30日(木)17時まで
- 一次審査(書類審査):令和7年12月末頃に結果通知
- 二次審査(面接審査・総合審査):令和8年1月中旬~2月上旬
- 交付決定・採択通知:令和8年2月下旬
- 助成事業開始:令和8年3月1日~(区分に応じて最長1年9か月または2年9か月)
- 中間報告:令和8年12月15日までに提出
- 完了報告・実績報告:終了後15日以内に提出
- 完了検査・助成金支払:報告確認後に助成金額確定・交付
助成対象事業の詳細
製品改良プロジェクト
市場ニーズに応じた製品改良を行うプロジェクトが対象です。改良の方向性は多岐にわたり、以下のような例が挙げられます。
- 機能追加・性能強化(例:耐久性向上、UI改善、小型化・軽量化)
- 効率化、省電力化、低コスト化(例:生産速度向上、電力削減)
- 実証データ取得や検証試験の実施
規格適合・認証取得プロジェクト
ISO9001、ISO13485、ISO27001、CEマーキング、FCC認証など、国内外の規格・認証取得に向けた取り組みを支援します。
特に輸出を視野に入れる企業にとっては不可欠な活動です。組織的なマネジメントシステム認証も対象ですが、製品規格取得との同時申請はできません。
助成対象経費の詳細
助成対象経費は申請区分によって異なります。
製品改良費(①・③で対象)
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費(購入・リース・レンタル含む)
- 委託・外注費、専門家指導費
- 産業財産権出願・導入費
- 直接人件費(上限350万円)
- 賃借料(上限150万円)
規格認証費(②・③で対象)
- 規格取得に必要な原材料・副資材費
- 規格対応の試験・評価用機器購入費
- 認証機関への審査料、登録料、申請料
- 外部専門家指導料、翻訳費、内部監査支援費用
申請方法
申請はJグランツのみで受付されます。
利用には「GビズIDプライムアカウント」が必要で、発行に時間を要するため早めの準備が不可欠です。
必要書類は以下の通りです(法人の場合)。
- 申請書(事業計画詳細の別紙含む)
- 製品説明資料(パンフレット、Webサイト等)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 納税証明書(法人事業税・法人都民税等)
- 直近2期分の決算書・法人税申告書等
- 見積書(高額経費の場合)
審査方法
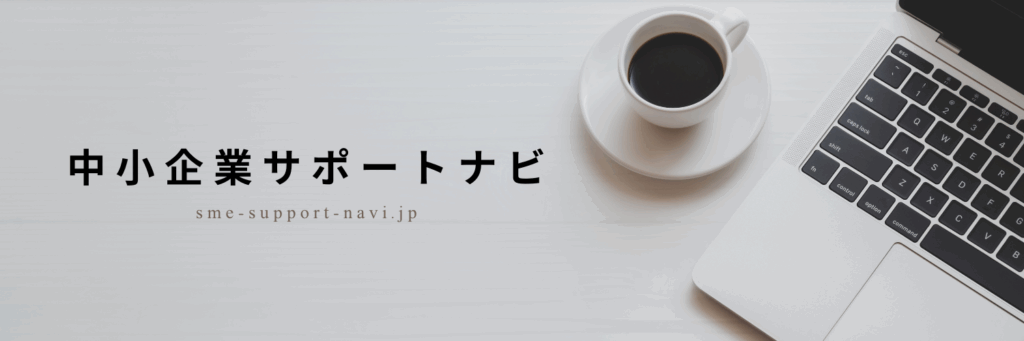
審査は以下の流れで行われます。
- 一次審査(書類審査)
申請要件の適合性、事業計画の実現性、新規性・市場性などを評価 - 二次審査(面接審査)
事業者によるプレゼンテーションと質疑応答を実施 - 総合審査
全体を通じて採否を決定
評価ポイントは、市場ニーズとの適合度、新規性、実現可能性、資金計画の妥当性などです。
過去の採択企業の特徴
過去の採択企業は、いずれも「明確な市場ニーズ」と「規格認証を通じた販路拡大」を強く意識している点が共通しています。
例えば、
- 医療機器分野でISO13485を取得し新市場参入を果たした企業
- 輸出先国の法規制に対応するためCEマーキングを取得した製造業
- 国内競争力を高めるためISO9001を取得し信頼性を強化した企業
いずれも、製品やサービスの改良+規格認証の取得が売上拡大に直結することを示しています。
申請成功のための実務チェックリスト
助成金の申請では「書類の不備」「要件確認不足」「スケジュール管理ミス」が不採択の原因になるケースが多く見られます。実務で確実に進めるために、以下のチェックリストを活用してください。
✓ GビズIDは早めに取得したか?
Jグランツ申請に必須のため、発行に数週間かかることを想定し、最低でも2か月前には手続きを開始しましょう。
✓ 必要書類をすべて準備できているか?
登記簿謄本、納税証明書、直近2期分の決算書などは発行に時間がかかる場合もあります。チェックリスト形式で管理すると漏れを防げます。
✓ 見積書は2社以上から取得しているか?
100万円以上の設備や外注費には原則として複数見積が必要です。不備があると差し戻しの原因になります。
✓ 申請テーマは明確に設定したか?
「製品改良」「規格認証取得」の目的を簡潔に示し、誰が見ても分かるテーマ名にしましょう。
✓ 事業計画は実現可能性を裏付けられるか?
単なる願望ではなく、売上予測や販路開拓の見込みを数字で示すことが重要です。
✓ 期限を守る体制を整えているか?
中間報告・完了報告は遅れると助成金交付が遅延、最悪の場合は不交付になる可能性もあります。スケジュール管理の責任者を明確にしてください。
審査で重視される3つのポイント
審査員は申請書類と面接を通じて、以下の3点を特に重視します。
市場ニーズと事業の適合性
助成金は「市場に求められているかどうか」が最も重視されます。市場調査の結果や顧客の声を示し、「なぜ今必要なのか」を明確に伝えることが大切です。
新規性と競争優位性
単なる改良や認証取得ではなく、「競合との差別化」「技術的な優位性」を示せるかが鍵です。既存製品との比較表や、競合が取得していない認証を狙う戦略は有効です。
実現可能性と継続性
どれだけ優れた計画でも、実行できなければ意味がありません。必要な人材・資金・設備が揃っているか、体制が整っているかを示すことが重要です。また助成金終了後も事業を継続できる仕組みがあるかどうかも評価対象です。
まとめ
「令和7年度 製品改良/規格適合・認証取得支援事業」は、最大500万円の助成を受けながら製品改良や規格認証取得に挑戦できる貴重な制度です。
しかし、採択されるためには
- 実務的な準備(チェックリストで漏れを防ぐ)
- 審査で重視される3つのポイントを押さえた計画立案
が不可欠です。
中小企業にとって、規格認証や製品改良は販路拡大・信頼性向上の切り札です。今回ご紹介したチェックリストと審査ポイントを意識しながら申請に臨めば、採択の可能性は大きく高まります。
申請を検討される際には必ず募集要項をご確認の上、ご不明な点は事務局等にご確認下さい。
募集要項:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000000egr5-att/05_R7kairyo_bosyuuyoukou.pdf